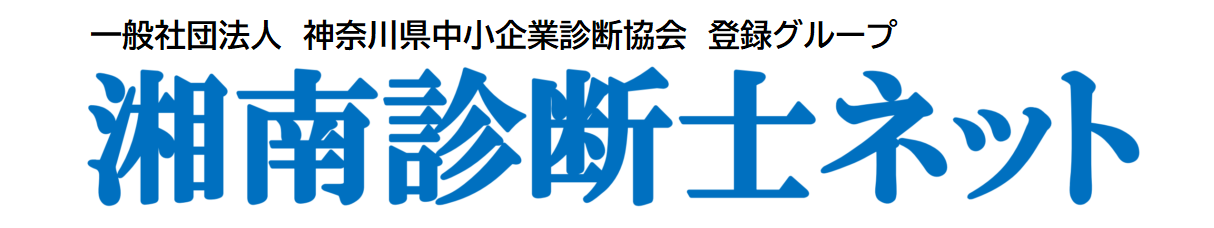中小企業診断士の仕事として経営支援以外に講演(企業や各種団体、学校での講師)や執筆があると言われています。 このブログ集の中に、私が過去に書いた雑誌記事の原稿が2本掲載されていますので、その事について書いてみます。
中小企業診断士の執筆活動
私が診断士になって最初の頃、大先輩の講演で「まず自分のブランドを作らないといけない。 その為には本を書かないといけない」と言われました。 確かに、中小企業診断士に限らずいろいろな世界で名前の挙がっている方々は、著書を持っていてそこを起点に活動されている方も多くおられます。
では、どうやったら本が書けるのか? その答えは「有名にならないといけない」 です。
つまり、鶏と卵でらちがあきません。 しかし、これも当然で、どこの誰ともわからない私が、本を書きたいと言っても(本当に読んでもらえるコンテンツを持っていたとしても)相手にされません。 私の知っている出版社の社長も、「持込原稿はいくらでもはいってくるが、その中から出版になる物はまず無い」 と言っていました。
サラリーマン時代は仕事の関係で専門雑誌の記事は結構書いていました。
独立してからは、中小企業診断士試験の練習問題と解説の本を4年続けて寄稿しました。 これでも共著者として巻末に名前は出ますが、いわゆる執筆活動と言えません。
指定された記事を書く
そこでこういう形も有ります。
ある組織で雑誌の原稿を書く機会を得ました。 雑誌記事は最初に企画がされていて、内容や文字数、レイアウトも指定されますので自由度は無いですが、書くことに専念できるという利点がありますし、私自身の知名度は(多分ほとんど)関係ありません。 中小小売業が大手のショッピングモールに出店して、その名前を生かして商売をするようなものです。
難しい注文に苦闘
このブログ欄に掲載されている原稿で与えられた題目は「中小企業白書の読み方」でした。 白書の事例を一つ取り上げて書くという事で、最初は「スーパーまるまつ」の事例が対象でした。
しかし、これは考えてみると大変な難題でした。 まず、原本は中小企業白書です。 したがって、必要な情報はちゃんと網羅されていて隙間は有りません。次に、予算と時間の関係で直接インタビューもできません。 白書をコピーして、「こう書いてあります。 終わり」 と言いたくなるくらいです。 つまり、公開されている情報と自分の知識・経験をミックスして、白書の内容をさらに正しく膨らませて読者が読むに堪える記事にするという大変な仕事だと気づいたわけです。 (記事の冒頭に、この企業の最初のPOSの導入は私がやったと書きましたが、それは事実です。 ただ、それは40年近く前の話で、この記事を書く助けには全くなりません)
とにもかくにも、いろいろな情報を私なりにミックス、整理して記事を書き上げたのがこの文章でした。
「ひまわり市場」は、その1年後です。 今度は、同じ編集長から直接お話しが入り、やらせて頂きました。 「前の記事が良かったから」と言っていただいたので、プレッシャーは有りましたが、前年同様の苦闘をしつつ書き上げました。
インタビュー記事
もう一つのタイプの執筆はインタビュー記事です。
いろいろな条件が決まっているのは前のタイプと同じですが、今度は相手の方に会ってインタビューし、文章にまとめるという作業が必要になります。
このインタビューのやり方は、実は、診断士として企業支援をするときの面談に非常に近いものです。 つまり、
- ①事前情報からテーマを考えておく
- ②インタビューではフリーに話していただくが、自分の考えたテーマに沿って、話が進むか考えながら質問する
- ③テーマが間違っていたら、即刻修正する
- ④まとまったストーリーにして、起承転結を明確にして記事にする
という流れです。 ここで「テーマ」を「企業の課題」に置き換えると、企業支援の時の面談になります。
このタイプは、数件書いており、下は紙ではなくネット上の記事ですが、その一例です。

読まれれば解りますが、これは志師塾という士業の為のビジネススクールの宣伝紙のようなページですので、結論はそのスクールを褒めるという暗黙の条件は有りました。 ただ、それとは別に、斎藤氏のお話は非常に魅力的で、楽しいインタビューが出来ました。
写真撮影

ところで、インタビューの必需品はカメラです。 この記事でも私が撮った写真が使われています。 冒頭の写真はインタビューの間に話しながらバチバチ撮った物なので、なかなか良い表情で撮れたと思っています。 ただ、事務所の外観は、実は、ホームページから許可を頂いて転載しました。 これは、インタビューの当日が大雨で、きれいな写真が撮れなかったためです。 現実にはこんな問題も発生するものです。 私は写真撮影が趣味なので一眼レフを持っていきましたが、無論、小型カメラやスマホでも写真は撮れます。 ただ、意図したような写真を撮るためには出来るだけ機能の高いカメラを使った方が良いと思います。
お勧め
非常に魅力的な方との出会いが有るのは、インタビュー記事の醍醐味ですし、上に書いたように、企業診断の面談とよく似ています。 この記事を読まれている診断士の方が、まだ経験されていなければ、いろいろな機会をとらえて経験されることをお勧めします。 ただ、インタビュー記事は現在-過去-未来というパターンで書かれます。 世の中には、フリーライターという方々が多くあり、皆さんが読まれるインタビュー記事も沢山ありますが、ほとんどがこのふわっとしたパターンに沿っているのを気付かれたと思います。
但し、企業診断の面談と全く異なる点も重要です。 インタビュー記事では、企業診断なら最重要項目である「私の提言は」を未来の部分に入れられません。 私はこの記事以降はインタビュー記事を書いていませんが、これに何となく不完全燃焼を感じためです。
新しいメディア
紙を前提とした記事以外に、今では ブログ、YouTube、 などでの発信も選べるようになっています。 いろいろな専門家の方が、大変立派な情報を公開されているので私も活用させて頂いておりますが、こういう現代のメデイアを使うことも今後は考えたいと思っています。